ウェブマガジン カムイミンタラ
 2008年05月号/ウェブマガジン第21号 (通巻141号) [ずいそう]
2008年05月号/ウェブマガジン第21号 (通巻141号) [ずいそう]
「君の手を握る!」―多喜二の手紙―
荻野 富士夫 (おぎの ふじお ・ 小樽商科大学教授)
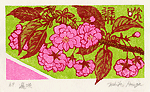
「遅咲」
版画:宝賀寿子
思想史から出発した私が、これまで取りあげてきた石川啄木や大杉栄・河上肇らはいずれも手紙の名手だった。繰りかえし借金を申し込む啄木、獄中の四季の移り変わりや読書の感想を丹念に書き込む大杉や河上の、手紙にあらわれた人となりにまず共振することで、それぞれの思想のありようにも関心を寄せていくことができた。
小林多喜二の場合もそうである。小樽旭展望台の多喜二文学碑に刻まれた「冬が近くなると、ぼくはそのなつかしい国のことを考えて」という、小樽をもっともよく表現した一節は、東京の豊多摩刑務所から、差し入れなどの世話をしてくれた村山籌子(かずこ)に宛てた獄中からの書簡にある。
「蟹工船」などの創作意図を語った多喜二書簡とは別に、その残された書簡群には、田口タキ宛のラブレターと豊多摩からの獄中書簡という二つの山がある。
田口タキ宛の最初の書簡(一九二五年三月二日)は「闇があるから光がある」で始まり、「私の最も愛している 瀧ちゃんへ」で終わる。タキとの手紙の往復は、二人の愛情を育てていくうえで何よりも大事なものだったと思われる。
多喜二は「万歳々々」(『原始林』一九二七年四月号)という小説にほほえましいエピソードを盛り込んでいる。「お恵」の手紙の「終りの彼の名前のところは何時でもインキが滲んでいる」、そして「彼はそこへ自分もキッスをした」。また、「メリヤスの股引」を贈って、お恵から「今日からは昼も夜も離さず肌につけている積りよ……」という返事がくると、「万歳だ、万歳だ、万歳々々」と喜ぶ。
これらは実体験に近いものに取材しているはずで、多喜二自ら「この位、いゝ気持で時々微笑しながら書いたものは、今まで絶無と云っていゝ」(「日記」二七年二月七日)と書いている。
もう一つの獄中書簡(一九三〇年夏から三一年一月)の多くで結びに使われるのが、「君の手を握る!」「此処から、皆の手を握ります」「心から君の手をにぎらせてくれ給え」などである。タキ宛にも「握手をおくる」と書く。すでに多喜二はレーニンの著作を通じてこの連帯の挨拶を知って用いたこともあったが、豊多摩の獄中で「チェホフの手紙」を読み(内山賢次訳『チエホフの手紙』が一九二一年に洛陽堂から刊行されている)、「終りに、あなたの小ッちゃいお手てをにぎります」に強く惹かれ、以後チェホフにまねて、この挨拶を多用することになった。
多喜二は出獄後にも、まだ獄中にいる友人に「固く手をにぎる、遠いこゝから」と書き送る。コンクリートの厚い壁に閉じ込められた独房から(また、独房へ)、親しい友人たちに向けて、この手のぬくもりの伝わる別れの言葉は、常に隣で語りかける温かな多喜二の人柄を想い出させただろう。
こうした人と人のつながりを大事にし、それぞれの生き方を見守ろうとするゆえに、それらが権力や権威によって蹂躙されることに、多喜二は「にえくりかえる憎悪」をもって対峙した。
母セキは、獄中の多喜二に手紙を書くために、文字を学び始めた。また、映画「母べえ」(山田洋次監督)で、獄の「父べえ」と残された家族をつないでいたのも手紙の往復だった。
