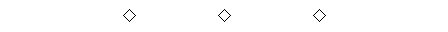ウェブマガジン カムイミンタラ
 2010年11月号/ウェブマガジン第30号 (通巻150号) [特集]
2010年11月号/ウェブマガジン第30号 (通巻150号) [特集]
女性自衛官人権訴訟 原告と弁護団の3年3カ月
2007年5月8日、国を相手に損害賠償を求めるひとつの訴えが札幌地方裁判所に起こされました。道内の航空自衛隊基地に勤務する女性自衛官が、同基地に勤務する男性自衛官から強制わいせつ行為を受けたとして、現職のまま提訴したのです。この裁判は若い原告(当時21歳)にとって、事件から3年11カ月、提訴から3年3カ月という長い闘いになりました。しかしこの間、81名の原告訴訟代理人はもちろん、「女性自衛官の人権裁判を支える会」(共同代表:影山あさ子、清水和恵、竹村泰子)や原告を応援する多くの傍聴者に支えられながら、2010年7月29日ついに勝利判決を勝ちとり、控訴期限の8月12日に国側の控訴断念を受けてその判決が確定しました。並々ならぬ勇気と決意で訴えを起こした原告の思いと、今回の裁判と判決のもつ意味を、訴訟代理人の佐藤博文弁護士と秀嶋ゆかり弁護士にお聞きしました。
ひとりのたたかい

■佐藤博文さん
・北海道十勝出身。北海道大学教育学部卒業。1988年に弁護士登録。
・「自衛隊イラク派兵差止北海道訴訟」原告代理人。
・PKOによる自衛隊が派遣された際は、自由法曹団の調査団員としてカンボジアを視察(1993年)。
■秀嶋ゆかりさん
・長崎県出身。早稲田大学法学部卒業。1989年 弁護士登録(東京)。 1997年 札幌弁護士会に登録変更。
・札幌に移ってから、DV事件やセクシュアル・ハラスメント訴訟等にも関わるようになり現在にいたっている。
-事件から提訴までの半年間、原告は基地内でどのような状況にあったのですか-
●佐藤 事件が起きたのは2006年(平成18)9月9日未明のことです。この航空基地はレーダー業務があるので山の上という人里離れた立地にあって、当時は全隊員180名のうち女性隊員がわずか5名、独身者は基本的に敷地内の宿舎に居住するのが決まりです。いわばこの隔離された「職住一体」の環境の中で、原告も他の女性隊員と共に、職場の上階にある宿舎で生活、勤務していました。
人間関係はというと、身分の序列によって規律・統制される組織ですから、階級の低い者は上司や先輩に逆らうことが許されないという特殊な社会です。
3曹の加害者Aは妻帯者なので基地内の宿舎に居住していませんでしたが、その日は24時間勤務のボイラー作業についていました。じつは加害者が、あろうことか勤務中に酒を飲んで泥酔し、深夜に女性宿舎に電話をかけて呼び出そうとしたのは、原告ではなく他の女性隊員です。原告は、その女性隊員は就寝中だからと断りましたが、「代わりに来てほしい」「他に2人の隊員も一緒にいる」と言われ、上下関係もあって断りきれなかったんですね。また、原告は女性隊員の最年長者だったので、加害者Aに非常識な深夜の電話をやめてもらおうという考えもあって、ボイラー室に行き、この被害に遭ったわけです(事件当時20歳)。
●秀嶋 原告は被害(強姦未遂)に遭ったことをその日のうちに上司に話しました。ところが、上司や基地司令のその後の対応をみますと、加害者をかばい、原告に対する保護・援助を怠っただけでなく、やがて原告を厄介者、問題隊員として排除する方向へ進んでいきました。
被害に遭った日と翌日の2日間、原告を夜間勤務させる。病院の受診を求める原告に、上司は「外科か、内科か?」とからかうように言い、婦人科の受診には男性上司の付き添いが必要であるなどの条件をつける。ようやく婦人科の受診が認められたのは、事件から3週間も経った9月30日のことでした。原告のお母さんが基地司令部に直接電話で抗議してからのことです。
さらに、原告が基地内で加害者と会わないよう勤務時間や食事時間を調整することをはじめとした職場環境に関する配慮をしない。原告を公的な行事に参加させない。さらには、原告に規律違反(夜間に宿舎から出歩いた、指定場所以外で飲酒した、など)があったとして、何度も取り調べをおこなう。被害内容を確認する際にも、男性隊員が聞いたり、男性隊員がいる前で犯行再現をさせられるなど、被害者として適切に扱われない中で、原告はひとりでたたかっていました。
熾烈(しれつ)な退職強要
●佐藤 原告に対する露骨な退職強要がはじまったのは、2007年の年明けころからです。というのは、07年3月は原告にとって、最初の任用更新の時期だったんですね。
自衛官には、任期制隊員と非任期制隊員の2種類があり、任期制隊員は、陸自が2年ごとに、海空自は最初が3年でそれ以降は2年ごとに、更新手続きがあります。民間企業でいうならば、任期制隊員のうちは契約社員で、試験に合格して下士官(最下級が3曹)になって初めて非任期制隊員、つまり定年まで勤務できる正社員となります。自衛隊は、任期制隊員といえども、本人によほどの落ち度や刑事事件などを起こさないかぎり、そう簡単に任用継続を拒否する(クビにする)ことはできません。
このときの任用更新手続きのスケジュールは、2006年12月1日が調査の基準日となり、志願書の提出期限が2007年1月15日、同年2月1日までに任用予定の内示がされることになっていました。
原告は、前年の12月5日ころに上司から直接面談を受けて任用継続の希望を伝えており、19日にはそのための健康診断を受けて「問題なし」の結果も得ていました。
部隊ではさまざまな手続きがありますが、担当者が書類などの段取りをし、本人は指示どおりに記入・押印するのがふつうです。原告は任用継続手続きについても同様に認識していました。
しかし、この手続きが初めての原告に対し、12月5日の面談で志願書の提出期限や必要な提出書類などの説明はいっさいなく、その後も書類を渡されていません。そして、上司が原告に志願書を提出したかどうかを確認したのは、任用を内示される2月1日から1週間もすぎた2月7日でした。
これは、厳格な規律を重んじる自衛隊では、絶対にあり得ないことです。上司たちが組織的かつ意図的に、原告に対して手続きをとらせないようにし、3月21日の任期満了期限までに退職に追い込むつもりだったとしか考えられません。
●秀嶋 志願書提出期限の翌日(2007年1月16日)、原告は上司から再度、今後のことを聞かれています。このときも、原告は「自衛隊の仕事も、通信制大学も、医療事務の資格取得も、ぜんぶやっていきます」と、引き続き自衛隊員として働く意志があることを伝えています。にもかかわらず、上司は、提出期限が過ぎていることを教えませんでした。
原告は、加害者の処分と異動を再三にわたって要請しました。しかし、基地では、相手の処分はもとより、異動もさせず、同基地でそのまま勤務させ続けました。
さらに、上司は原告に、「おまえ、悲劇のヒロインじゃないんだぞ」、「おまえ終了だよ。終了」などのひどい言動を重ね、原告に追い打ちをかけました。
●佐藤 退職強要がはっきりしたのは、例の、上司から志願書を提出したかどうかを聞かれた2月7日です。
原告はこの日、勤務開始の直後から1時間にわたって、直接の上司から、ほかの隊員もいるなかで、「おまえアホか。ここまでこじれたら、自衛隊ではやっていけないんだよ」などとなじられ、「休み好きなだけやるから帰れ」「帰ってくるときには分かっているな。お母さんに辞めるという同意書、書いてもらってこいよ」と、有給休暇の消化と退職を迫られました。そして、「帰省中に考える事項の参照」、再就職に関する本の一部のコピー、退職願の用紙とを渡されたわけです。
●秀嶋 有給休暇は、本来、労働者の権利ですが、上官が原告に取得を実質的に強要し、しかも、勤務の継続を希望している原告に、あえて退職願を渡したという行為は、退職強要そのものです。
原告はその前日、受け続ける誹謗中傷の攻撃から、体調を崩して倒れ、病院にかかるほどの心身状態でした。そんな状態のときに、直接の上司になじられ、退職を迫られました。心身ともに疲れはてた原告は、とにかくその場から逃れたい一心で、有給休暇の取得と帰省を受け入れざるを得なかったのだと思います。
その帰省中にも、原告は、上司から電話で「2年間継続しても、俺はもっと厳しくするつもりだ」「2年間外出禁止にする」「大学のスクリーニングに行かせない」など執拗に退職を促されています。
●佐藤 東京から戻るとすぐ、2月22日ですが、原告は上司たちに囲まれ、「おまえのハンコ、持ってきたからな。押せよ」と自分の印鑑を見せられて、目の前に置かれた退職届に押印するよう言われます。
原告はこのころ、もう辞めざるを得ないと思いはじめていましたが、それが自分の意志ではなく、「退職を迫られたから」なので、彼女はその退職届に判を押しませんでした。次の日も次の日も、印鑑を押すように言われましたが、彼女は最後まで押さなかったんですね。
初めての希望
-その後、原告はどのようにして佐藤さんや秀嶋さんと出会い、提訴を決意するに至ったのですか-
●佐藤 原告が僕のところに相談に来たのは、彼女が東京から戻ったその日、明日からまた勤務が始まるという2月21日のことです。
原告は帰省中も思い悩んで、東京に住んでいたお父さんに相談したんですね。で、お父さんも、これは親の力ではどうにもならないと、知り合いの弁護士さんに相談した。そうしたら、「札幌にある北海道合同法律事務所に、自衛隊イラク派兵差止北海道訴訟の裁判をやっている弁護士がいて、『自衛隊と家族のなんでも110番』というのをやっている。相談してみたらどうか」と言われたんですね。そして、お父さんからその話を聞いた原告が、帰ってきたその日すぐに僕のところに来たわけです。とても思いつめた様子で、暗い顔をしていました。
で、そのときの彼女は、「もう辞めるしかないと思っているけれど、どうしても納得がいかないから、辞めたあとでも裁判とかなにか闘える方法はないか」というのが私への相談でした。
僕が、自衛隊のやっていることは不当だよ、あなたは悪くないよと言うと、彼女は少し楽になった様子でした。あとで彼女から聞いた話ですが、基地内で責められているうちに、だんだん自分が悪いのだと思い込むようになっていたらしい。
それが、僕の話を聞いて、自分は悪くない、と気がついたと言います。彼女は次の日、上司に呼ばれてハンコを押せと言われたときに、「やめる方向で考えているけれども、辞めさせられるのだから、自分からハンコを押すことはできません」とぎりぎり判を押さないで頑張ったんですね。
-原告は陳述書のなかで、佐藤弁護士に出会えたことを「初めての希望だった」と述べています。闇のなかで一条の光を見る思いだったのでしょうね-
現職のまま提訴
●佐藤 しかし、裁判でたたかうにしても、僕はあのときの原告に「現職のままで頑張れ」とはとても言えませんでした。あのひどい状況です。自分の娘と同じ年ごろの女性が、これからたったひとりで基地に帰るんです。提訴すれば、職場である基地内で、ますます追いつめられることになります。思いつめて、疲れ切った顔をしていましたからね。「頑張れ」とはとても言えない。
それに、こういう人たちの苦痛を少しでも軽くすることは、われわれとして当然のことです。それで、彼女には「無理しなくていいよ」「辞めてもいいんだよ」と言ったんです。
●秀嶋 それでも、原告は現職のままたたかうことを決意しました。佐藤弁護士と会って1週間後の2月28日、原告はまず警務隊に告訴状を提出しました。警務隊は、自衛隊の秩序維持のため、犯罪捜査などの警察業務や警護などの保安業務をおこなう、いわば自衛隊の警察です。これでようやく加害者に対する刑事捜査が始まりました。
この日は、原告のお父さんも基地を訪れ、上司たちの退職強要に対し強く抗議しました。これは原告にとって、たいへん心強かったのではないでしようか。
●佐藤 原告が提訴してたたかうと決意した時、私は彼女を支える体制をつくることが大前提だと思いました。このとき、誰に声をかけたかというと、イラクで人質になった高遠菜穂子さんや今井紀明くんの救出のために、中心となって活動した影山あさ子さんや竹村泰子さん、七尾寿子さんたちだったんですね。彼女たちにはもう、そういうノウハウがありますから、ワーッと集まって、「女性自衛官の人権裁判を支える会」をたちあげ、サポート体制をつくってくれました。
僕はセクハラ事件をやった経験がなく、ひとりでは大変だと思い、秀嶋さんに協力をお願いして弁護団に入ってもらったわけです。最終的には僕らのほかに79名の弁護士が訴訟代理人に加わってくれ、原告を支えることになったんです。
●秀嶋 そして2007年5月8日、原告は札幌地裁に提訴しました。事件から8カ月がたっていました。
-この年はちょうど、1月9日に防衛庁が省に格上げになって、前日まで防衛庁長官だった久間章生氏(きゅうま あきお・自民党)が防衛大臣になったあとでしたね-
●秀嶋 一般的に、性犯罪やセクシュアルハラスメントは、密室で被害に遭うことがほとんどであるため、目撃者などがいません。裁判では、被害に遭った側がどのような被害に遭ったかを立証する必要があります(立証責任)。しかし、この立証作業は、被害者にとって、事件の記憶をなんども思い起こさせられるひじょうに辛い作業となります。
しかも今回は、民間企業以上に内部の協力者を得ることが難しい自衛隊という「密室」で起きた被害であり、裁判を起こす場合には、国を相手(被告)にしなければなりません。長いたたかいのはじまりでした。
●佐藤 あとになって原告が言ったことですが、当時はワラにもすがる思いで裁判を起こすことになったけれども、まもなくして、頼んだ弁護士が『反自衛隊』の弁護士だと知って、驚いたそうです。彼女は自衛隊が敵視するようなとんでもない弁護士に頼んだと思ったそうです。
でも、2007年3月に出版された箕輪さんたちの『我、自衛隊を愛す、故に、憲法9条を守る-防衛省元幹部の3人の志-』(※1)という本を読んだようです。ご存知のように、故・箕輪登さんは、専守防衛の考えから、2004年1月に「自衛隊イラク派兵差止訴訟」を起こした元防衛政務次官です。私がその箕輪さんの訴訟代理人をやっているということで、安心したと話してくれました。
提訴を決意した原告の思い

(※1)
『我、自衛隊を愛す、故に、憲法9条を守る-防衛省元幹部の3人の志-』
著者:小池清彦 竹岡勝美 箕輪 登
発行:2007年3月1日 (株)かもがわ出版
小池清彦=1937年(昭和9)、新潟県加茂市生まれ。1960年に東京大学法学部卒業後、防衛庁に入庁。英王立国防大学に留学後、防衛局計画官、官房防衛審議官、防衛研究所長、教育訓練局長を歴任し、1992年に退官。1995年から2010年10月現在まで加茂市市長。
竹岡勝美=1923年(大正12)、京都府亀岡市生まれ。1948年に京都大学法学部卒業。同年、国家地方警察本部に上級職として入庁。岡山、鳥取両県の県警本部長を歴任。1976年、防衛庁人事教育局長に。その後、官房長、調達実施本部長を経て、1980年に退官。
箕輪 登=1924年(大正13)、北海道小樽市生まれ。北海道大学医学専門部を卒業し、医師になる。1967年以来、衆議院議員(自民党)として8期連続当選。防衛政務次官、郵政大臣などを歴任し、1990年に引退。2004年1月、『自衛隊イラク派兵差止北海道訴訟』(箕輪訴訟)を起こすが、2006年5月に死去。
箕輪訴訟を皮切りに『自衛隊イラク派兵差止訴訟』は全国で起こされたが、2008年4月、名古屋高裁が控訴を棄却したものの、判決理由で「イラクでの航空自衛隊の活動は憲法違反である」との画期的判断を示し、その判例を残すため、箕輪訴訟もほかの訴訟と足並みをそろえて終結となった。
-性犯罪に遭った女性が口を開くことは、容易なことではないと思います。原告がその迷いを乗り越え、しかも現職のままで国を訴える決意をしたのは、どんな思いからだったのでしょうか-
●佐藤 原告は2004年(平成16)3月に東京都内の高校を卒業し、航空自衛隊に入隊しました。働くならば人の役に立つ仕事がしたいと思っていた原告は、親友に誘われて行った自衛隊の募集事務所で阪神大震災の災害派遣の話を聞いて感動し、入隊を決めたそうです。
北海道の基地に配属になったのは2005年4月で、8月から通信電子隊電子整備班に配属になりました。翌06年2月に空士長に昇進し、6月には北警団英語弁論大会「初級の部」で準優勝するなど、優秀な女性です。
家庭の事情から大学進学をあきらめた原告には、ぜひ実現したい夢がありました。就職してお金を稼げるようになったら、『プラン・ジャパン』(発展途上国の子どもの生活と教育を支援するプログラム)を始めること。そして、自分自身も通信制大学で勉強をすること。入隊した原告はプラン・ジャパンのプラン・スポンサーを始め、弟と同じ年齢のバングラディッシュの男の子のスポンサーとなり、いまもその活動を続けています。事件の直前には、10月から通信制大学に入学することが決まっていました。
そんな夢いっぱいの20歳の女性が、感動と誇りをもって入隊した自衛隊の中でこの被害に遭い、その自衛隊から、ボロボロになるまで繰り返し傷つけられ、追いつめられたのです。
●秀嶋 それでも、原告は、職場である自衛隊に踏みとどまって国を相手にたたかう決意をしました。原告はその理由を、2007年6月11日におこなわれた第1回口頭弁論の意見陳述でこう表明しています。
「自衛隊の中にはたくさんの問題があります。部隊にはカウンセラーが配置されていますが、(中略)『自分は幹部自衛官には意見できない』といわれました。(中略)自衛隊には労働組合もありませんし、被害者にとってはとても不利な状況なのです。国は、一刻も早く事実を確認し、改善をしてください。もしこのまま事実を隠そうとすれば、同じ過ちはくり返されます。そうなればよい社会はつくれないし、美しい日本はつくれないと思います。私は、私の事件を通して、私のような思いをする女性が二度となくなるようにしたいです」。そして、「私の踏みにじられた人権を取り戻すため、同じ経験をした女性の人たちに勇気を与えるため、たたかいます。」と。
●佐藤 退職強要は2月28日に警務隊が入ってから一端おさまっていましたが、5月8日の札幌地裁への提訴後、原告への嫌がらせはますますひどくなりました。
提訴の翌日、原告は上司から「奥の部屋」と称する物置部屋への異動を命じられました。
われわれはこれについてすぐさま抗議し、撤回させましたが、原告が現職のまま裁判を起こすということは、法廷と職場、その両方でたたかうことなのです。
●秀嶋 第1回弁論のこの日は、加害者がようやく遠地に異動になった日でもありました。基地へ再三の申し入れを行っていた、原告と弁護団と「支援する会」の、実質的には大きな一歩でした。
3つの争点
-裁判は、どのような争点でたたかったのですか-
●佐藤 われわれ訴訟代理人は最初、原告の思いを汲みとり、次のような3つの争点を考えました。
(1)強制わいせつ行為の事実の認定。(2)被害者である原告に対する事後の対応(事件後の保護・援助)が、きちんとなされていなかったという事実の認定、(3)最終的に部隊として退職強要という排除に出たことです。
●秀嶋 原告は、事件直後から様々な二次的な被害を被っていましたが、提訴後も任用継続にはなったものの、ひじょうに孤立的な扱いを受けていました。裁判長を含めて裁判官が交代した時期に、事後の様々な自衛隊の原告への対応について、整理をし直し、裁判所の判断対象をしぼった経過がありました。
裁判での主な争点は、(1)性的加害行為の有無と内容、(2)自衛隊の原告への退職強要を含めた事後対応の違法性、(3)原告が(1)(2)によって被った損害 でした。
-裁判が始まると、傍聴席にはスカーフとかアクセサリーとか、オレンジ色のものを身につけた人がたくさん来ていましたね-
●秀嶋 オレンジ色は、原告のラッキーカラーですが、支える会で、何とか彼女を元気づけようと考え出した支援の方法のひとつでした。
たくさんのオレンジ色の花が咲いているようで、原告の裁判の時は、法廷がパッと明るくなりました。
-国側は第1回から第3回の弁論まで「不知(ふち)」と返答していました。この「不知」とはどういうことですか-
●佐藤 答弁の仕方には大きく3つあって、「認める」「認めない」「不知」という返答があります。「不知」というのは、「訴えの内容について、自分たちは体験していないから分からない、知らない」とか、「それについて認めるとか認めないとか返事ができる情報を持っていないので、分かりません」という意味の返答です。
国側は第3回の弁論まで、当事者なのに「そんなことは知らない」という返答をしてきたわけです。こんなことは、欧米では、裁判にまじめに対応しない態度ということで、法廷侮辱罪にあたるような非常識な態度です。
●秀嶋 国は、途中まで性的加害行為があったかどうかについて、「不知」と主張し続けました。事件直後に原告が被害を訴え、基地での調査が行われていたはずにもかかわらずです。私たちは、「不知」という国の主張に驚き、ひじょうに不誠実であるとの怒りももちました。
2007年12月21日の第4回弁論で、国は、それまでの「不知」を撤回し、ようやく内容について答えてはきました。ただし、性的加害行為については、「合意」であったとの主張でした。
-国が態度を変えたのには、何か理由があったのでしょうか-
●佐藤 国が不知から認否に転じた内部事情まではよくわかりません。僕の推測で言うと、国側が、全面的に争うのか、それとも、争わないでうまく折り合いをつけられないか、探りながら裁判に応じていたんだと思うんです。
●秀嶋 事件からこれだけ時間が経過していて、懲戒処分の取り調べもやっていて、警務隊も入ったわけですし、知らないわけはありません。まったく無責任としか言いようがありません。われわれが、提訴からもこんなに時間がたっているのに、「不知とは何事だ」と法廷で厳しく批判したことも影響したと思います。
国、責任について全面的に争う姿勢
「国又は公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずる」
●佐藤 2008年2月7日の第5回弁論から、それまでの単独法廷が合議法廷に変わり、裁判官が3人になりました。合議になる基準はとくにありません。三人よれば文殊の知恵じゃないですが、裁判所として、一人の裁判官で判断するより、複数の裁判官で慎重に判断したほうがいいとなったときに合議体となります。
●秀嶋 国はさらに、性的加害行為は「合意に基づいていた」という主張に加えて、本件は、国が国家賠償法1条(※2)の責任を負う場面ではない、と主張していました。
国家賠償法1条は、「公務員が、その職務を行っているとき、あるいはその職務に関連するとき以外のことについては、国は責任を負わない」という規定です。
しかし、原告に対する性的加害行為は、上官が勤務中に勤務場所内で犯したものですから、「職務を行っているとき」にあたることは明らかです。この点でも、国の主張は納得のいかないものでした。
防衛省へ申し入れ
報告集会や署名運動も全国各地で展開
●佐藤 裁判の一方で、原告とわれわれ弁護団と「女性自衛官の人権裁判を支える会」は、第1回弁論の直後から、防衛省への直接的な申し入れを開始しました。
最初の申し入れは07年6月15日。前日までは待合所での書面受け取りだけとされていましたが、紙智子議員(参)ご本人と、岡崎トミ子議員(参)・福島瑞穂議員(衆)の両秘書が同行してくれ、各議員事務所からの電話もあって、本庁舎会議室で総務部広報室関係者と直接面談し、原告に対する不当な対応への抗議と早期解決を要請しました。
女性国会議員のみなさんからは、この後もなんども協力をいただきました。08年1月25日の4回目の申し入れの際にはまた紙智子議員が同席してくれ、加害者と上司の厳正な処分と、自衛隊でのセクハラ被害の実態調査、再発防止策を強く求めましたし、このあと参院議員会館で開いた院内集会にも多数の議員が出席され、私からの事件報告と意見交換などをおこないました。このときは原告も一緒に行って、超党派の女性議員の前で事件のことを訴えたんですよ。
●秀嶋 報告集会や勉強会、署名運動や募金なども全国各地でおこないました。報告集会は07年6月15日の東京を皮切りに、札幌、名古屋、青森、室蘭、広島、旭川などで開き、裁判への理解と支援を広く呼びかけました。
また、08年2月23日には「北海道議会、札幌市議会の女性議員と市民の 女性自衛官人権裁判学習会」を開き、08年4月21日には佐藤弁護士が「東大ジェンダーコロキアム」(上野千鶴子教授主宰)で話をする機会がありました。同年9月17日には一橋大学の佐藤文香准教授を講師に迎えて、公開学習会「軍事組織とジェンダーを考える」もありました。
今回のように国など大きな組織を相手にたたかうには、このような世論を広げる取り組みも、とても重要なのです。
そして、24,000筆ちかく集まった署名のひとつひとつ、送られてくる激励のメールひとつひとつが、原告を励まし続けたと思います。
自衛隊、原告の2回目の任用継続を拒否
原告は事実上の解雇に
-原告は2回目の任用継続を拒否され、事実上の解雇となりました。これについては、どのような形でたたかったのですか-
●佐藤 09年1月30日、原告は基地司令から、2回目の任用継続を拒否する旨の通知書を手渡されました。浜田靖一防衛大臣(自民党)のときでした。あれは原告にとって、たいへん大きなショックだったと思います。
原告は自衛隊に誇りをもっていましたし、自衛隊の仕事が好きでした。自分の職場である自衛隊が良くなってほしい、だから現職のままで国を相手に裁判を起こしたわけです。このときも自衛隊員を続ける意志は変わっていませんでした。
裁判を起こしていても、仕事はきちんとしていましたし、このときの健康診断もクリアしていました。なによりも、過去5年間に空自で任用拒否になったのはたった一人、これまでほとんど例がなかったからです(※3)。
(2002年度~2007年度)
●陸上自衛隊=43,000名中 なし
●航空自衛隊=8,200名中 1名
●秀嶋 任用継続拒否によって、原告は裁判を抱えているだけでも大変であるのに、生活手段を失い、通信大学での勉強継続も困難になります。原告とわれわれ弁護団はすぐに抗議し、原告から、個人情報の開示請求も行いましたが、全部黒塗りで「非開示」でした。任用継続拒否の理由は現在まで明らかにされていません。民間企業であれば、解雇された労働者は、企業に、解雇理由を文書で出すよう求めることができると法律で定められていることに照らしても、自衛隊であるから、拒否の理由を当事者に説明しなくて良いというのは、ひじょうに不合理であると思います。
原告は2月16日、このことを記者会見で公表しました。そして翌17日付で、浜田防衛大臣に撤回を求めました。これは新聞その他に取り上げられ、全国に知らしめることになりました。
紙 智子(共産党・参)
神本 みえ子(民主党・参)
岡崎 トミ子(民主党・参)
谷岡 郁子(民主党・参)
相原 久美子(民主党・参)
今野 東(民主党・参)
大島 九州男(民主党・参)
郡 和子(民主党・衆)
辻元 清美(社民党・衆)
(順不同)
●佐藤 3月3日には、紙智子議員はじめ超党派の国会議員9名(※4)がわれわれと一緒に、渡部厚人人事教育局長と面会し、防衛省に対して(1)任用継続拒否の理由について納得のいく説明をすること、(2)任用継続の拒否が裁判を理由とするものであるならば直ちに撤回すること、を強く申し入れましたが、結局は明快な理由の開示もなく、原告は3月21日に「任期期限満了」ということで追い出されてしまいました。
原告は、女性としての尊厳、人間としての人権、労働者としての権利まで奪われたのです。
●秀嶋 この原告の任用継続拒否に対しては、私たちも、どのように対応するかずいぶん悩み、議論しました。任期制の勤務の継続拒否であり期限の定めのない雇用の場合の解雇とは残念ながら異なること、公務員についての勤務継続拒否は、民間企業の解雇の違法性を争うよりも一般的にハードルが高いこと、原告の負担などを考慮しながら、原告とも何度かやり取りし、最終的には、あらたに国を相手とする裁判を起こすことではなく、その1年前の退職強要と今回の任用継続拒否が連続した対応であり、原告の職場からの排除=究極のパワーハラスメントでもあるとの趣旨で、主張を補充しました。
加害者は停職60日の懲戒処分 刑事事件は不起訴に
●佐藤 この間、加害者が停職60日の懲戒処分になったのは、2月27日のことでした。加害者は事件を起こした07年9月から、じつに1年半ものあいだ、具体的な処分を何も受けていなかったわけです。
-素人の感覚としては、加害者が停職60日、原告は事実上の解雇、というのは納得がいきません。加害者はこれから定年まで自衛隊にいられるわけで、もっと重い処分を求めることはできなかったのでしょうか-
●佐藤 一般に、加害者の処分を求める手段は、「懲戒処分」「刑事訴訟」「民事訴訟」の3つがあります。
「懲戒処分」というのは、企業など組織のなかで規律違反や非行行為などを処分するものです。基地司令では事件が起きた4日後の2006年9月13日に、原告に対する懲戒処分の調査開始を命令しましたが、加害者に対してもおそらく同じ日に取り調べがスタートしていると思います。
じゃあ、なぜ原告が懲戒処分を受けるのかというと、「あんな夜中に宿舎から離れたおまえが悪い」「おまえも指定場所以外で飲酒しただろう」と。それを理由として、たびたび原告の取り調べをおこないました。それは、原告への圧力にほかなりませんが、その懲戒処分については結局、09年2月27日に「原告、加害者をふくめた隊員56名を懲戒処分にする。原告を訓戒、加害者を停職60日」にして終わりました。
この結論を見てわかるように、「彼女の一人勝ちという処分にはしないよ」と。「みんな酒を飲んだりして規律を乱しているんだから、全員処分するよ」と。まあ、日本が得意とする総懺悔(ざんげ)方式で加害者の処分を終わらせたんですね。これが懲戒処分の流れです。
●秀嶋 本来であれば、加害者は懲戒解雇になり、被害者に対しては損害賠償や休職による休養など、できるかぎりの対応をするだろうと思います。しかし、彼女に対してはむしろ、懲戒処分のための事情聴取までしたわけです。そしてこのとき、原告は弁護士の立ち会いを求めたのですが、自衛隊には弁護士をつける権利はない、というやり取りがずうっと続いたのです。
代理人の私たちは、国相手の裁判と同時に、自衛隊の中で孤立している原告への対応もひじょうにエネルギーを要しました。
●佐藤 加害者の「刑事事件」については、原告が退職強要を乗り越えて1回目の任用が継続され、07年2月28日に警務隊に告訴状を出したときから刑事捜査が始まりました。しかし、警務隊はしょせん自衛隊の中の組織です。この事件が警務隊から札幌地方検察庁へ送られたのは6月のはじめ、つまり原告が5月8日に民事訴訟を起こし、第1回の口頭弁論がおこなわれる前で、それまで放っておかれたんですね。
ところが、札幌地検はその年の12月27日、この加害者を「不起訴処分」としました。密室でのことなので、証拠不十分ということでした。
それで、原告は翌08年1月31日に、札幌検察審査会に審査の申し立てをおこないました。「札幌地検の不起訴処分に納得がいかない」ということで、異議申し立てをしたわけです。
これに対して札幌検察審査会は、08年9月18日、「札幌地検の不起訴処分については問題なかった」という結論を出しました。
残念ですが、刑事事件としての手続きはこれで確定し、終了になってしまいました。
●秀嶋 なお、被害者が加害者やその雇用主に対し、主に損害賠償を求める裁判は「民事訴訟」と言います。今回のように、原告が国に賠償を求める裁判も、「民事訴訟」です。
自衛隊の人権を守ることは
民主主義を守ること
07年度 148人
うち性犯罪は90件(61%)
08年度 170人
うち性犯罪は98件(58%)
しんぶん『赤旗』より
(2010年9月7日付)
-自衛隊に対しては合憲とみる人と違憲と見る人がいますが、そうした考え方の違いを超えて今回の被害者を応援したのはなぜですか-
●佐藤 最近は自衛隊員の不祥事が多発していて問題になっています。深刻なのは、売春やセクハラなどの性犯罪がその事案の半数以上を占めている(※5)ことです。
一方で、僕は今回の裁判で、原告のように不当な理由で懲戒処分の取り調べを受けるというときに、自衛隊員には弁護士をつけることが認められていないことを初めて知りました。これにはびっくりしました。正しく調査・判断されれば問題はありませんが、隊員にとって懲戒処分は、自分の出世にも大きく影響します。そのときに、隊員たちは自分の身を守るものがないのです。

(※6)
『この身死すとも「これだけは言いたい」』
著者:長谷川慶太郎 田母神 俊雄
発行:2009年4月22日 (株)李白社
長谷川慶太郎氏
1927年(昭和2)生まれ、京都府出身。1953年大阪大学工学部を卒業。1955年~1963年産業新聞社記者を経て1963年に経済評論家として独立。証券アナリスト、評論家業を営む。
軍事評論家になりたかったが太平洋戦争の終戦で叶わなかったと語り、自衛隊幹部学校、防衛省防衛研究所一般課程の非常勤講師を30年以上にわたり務めている。
田母神 俊雄氏
1948年(昭和23)、福島県に生まれる。福島県立安積高等学校から防衛大学校に入学。卒業後航空自衛隊に入隊。第6航空団司令、統合幕僚学校長、航空総隊司令官を経て、2007年3月、第29代航空幕僚長に就任。
2008年(平成20)10月、民間の懸賞論文へ応募した作品が最優秀賞を受賞。これが政府見解と対立するものであったことから、浜田靖一防衛大臣から幕僚長の職を解かれて航空幕僚監部付となる。「航空幕僚長たる空将」から空将となったことにより、11月3日をもって定年退職。
●秀嶋 それに、刑事事件の捜査は警務隊がおこなうということは、意外と知られていません。警察官ではないのです。
-『この身死すとも「これだけは言いたい」』(※6)のなかで、長谷川慶太郎氏が「自衛隊の犯罪発生率は日本全体にくらべると低い。上官の命令に忠実に服し、どんな行動もとれる軍隊だ」と言い、田母神俊雄氏も「自衛隊はクオリティーの高い集団。不祥事対策委員会などいらない。外部からああだこうだと言うことは間違っている」と言っていますが-
●佐藤 自衛隊のなかでは、セクシャル・ハラスメントばかりでなく、イジメやリンチも頻発しており、隊員の在職中の自殺は、1年に100件ちかく起きています。そして実際に、家族や遺族による裁判が全国でたくさん起きてきていますし、提訴予定の事件もいくつもあります。
●秀嶋 厳しい上下関係の組織のなかで、しばしば、人権が侵されることが起きているんですね。一方で、加害者の処分は、一般よりもはるかに軽く済まされている。女性自衛官が現職で提訴した今回の裁判は、今までほとんど表に出てこなかった自衛隊内の性暴力被害が、裁判の形で公になったという意味で、とても大きな意義があります。
一方で、彼女のような被害に遭った自衛官は、過去にも少なくなかったと想像されます。その被害が公にならないままに葬られていたことを考えると、組織全体として、原告が被った被害を本当に教訓として、再発防止をはかってほしいと心から願います。
-自分の管轄組織の職員を守れないような国は、国民を守れない。部下を守れないような上司なら、国は守れない。そして、それを許したり無関心な国民なら、自分たちの平和は守れない…今回の裁判は、私たちにそういう戒めも気づかせてくれますね-
「精強さ」って いったい何?

(※7)
『自衛隊風雲録』
著者:田母神 俊雄
発行:2009年5月20日 (株)飛鳥新社
◆221P~「守屋次官とのファーストコンタクト」をみると、当時航空幕僚長の田母神俊雄氏の耳にもこの事件のことがしっかりと届いていたことがわかります。「いわばよくある男女間の"いざこざ"の類い」と述べ、また、「今後我々がやれることは部隊を守るにはどうするかということだ」などを見解として示しています。
防衛省内で深刻な問題との認識があったことを自ら明らかにしています。
●佐藤 国側は、自衛隊の職務の特殊性ということで、第一書面で「精強さ」ということを言ってきました。僕はこれを見てびっくりしたわけです。「精強さ」なんて、いままでぜんぜん聞いたことがない言葉で、自衛隊法とかいろんな法律を読んでも、この言葉はどこにも出てこないのです。
「精強さ」というのは、厳格な軍紀の保持を意味し、世俗的に言えば、男らしく強くなければいけないという意味です。彼らのあいだでは、あたかもそれが自衛隊の職務の特徴であり、組織運営のときの規律基準であり、それによって人権が制約されることもある、というふうに、彼らのすべてに貫かれている価値基準になっているんですね。つまり、男女の問題やセクシュアルハラスメントを自衛隊ではいちいち取り上げていられないと、オーバーにいえばそういうふうにも聞こえる言葉でした(※7)。この「精強さ」という言葉が、自衛隊法には出てこないのに、自衛隊の中ではいろんなところに出てくるんです。
日本国憲法は、「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」を三大原則としています。彼ら自衛隊も、日本の法律に基づいて動かなければなりません。この「精強さ」という考え方は、日本国憲法の「基本的人権の尊重」に反することになります。ですから僕は、これはどういうことなんだ、と追及しました。
(※8)男女雇用機会均等法
・1972年(昭和47)7月1日「勤労婦人福祉法」施行
・1986年(昭和61)「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(男女雇用機会均等法)」施行
・以後、1997年(平成9)10月1日、1999年(平成11)4月1日、2007年(平成19)4月1日に改正が加えられ、現在にいたる。
原告が勝訴した2010年7月は、1972年「勤労婦人福祉法」施行から38年、1986年「男女雇用機会均等法」施行から25年目を迎えた。
●秀嶋 セクシュアルハラスメントについては、男女雇用機会均等法(※8)という法律や一般の国家公務員に適用される人事院規則の中でも、雇用主の配慮義務が定められています。つまり、セクハラは加害者個人に責任があるばかりでなく、雇用主が、積極的にセクシュアルハラスメントを防止する措置を講じる義務がある。万一セクシュアルハラスメントが職場で発生した場合には、早い段階で被害者への保護、加害者への処分などを含む職場環境の整備をはからなければ、雇用主(企業ないし使用者)も独自に責任を問われる、という法整備がなされています。
国側は、自衛隊にも、上記のような法律と同じ内容のさまざまな通達などを出しており、セクハラ防止の教育も、防止措置も講じている、と主張していました。
そのことと、職場内で生じた性的加害行為(セクシュアルハラスメント)について、国の責任がないと主張することは、矛盾しているとしかいいようがありません。
現地調査を実現 裁判長も基地内へ
-2009年5月21日の第12回弁論で橋詰均裁判長に代わり、裁判が大きく進展しました。橋詰裁判長は、神戸地裁のとき、敗戦の混乱の中で中国に置き去りにされた「残留日本人孤児」が、国に対して「早期帰国や帰国後の自立支援の義務を怠った」として全国10カ所で起こしていた裁判のなかで、唯一、原告勝訴の判決を書いた裁判長でしたね-
●佐藤 このころになると、裁判は弁論から進行協議に入り、それまで2カ月に1度だった法廷が1カ月に1度の早いペースで進みました。提訴からまる2年が経過していましたし、国側との書面や証拠のやりとりもそろそろ整ってきましたので、われわれは、この裁判長でいっきに裁判を終わらせようと考えました。
-進行協議の傍聴も許されたのは、めずらしいことと聞いたのですが-
●佐藤 進行協議というのは、ラウンド法廷とかラウンドテーブル法廷ともいって、双方の代理人と、裁判長、裁判官が平服でひとつの円卓を囲み、争点の整理をするものです。非公開が原則です。
今回は12回の口頭弁論のあと、7回の進行協議をおこないました。最後の進行協議で、採用する証人を決め、証人尋問から最終弁論、判決までの日程を決めることが多く行われています。
●秀嶋 弁護団の申し入れで、6回目の進行協議は基地内でおこなうことになりました。進行協議とはいうものの、実質的な現地調査が実現しました。国側は、「必要な写真は提出しているので現地調査は必要ない」と反論していましたが、弁護団から原告が当時置かれていた状態を体感して欲しいと強く要請し、橋詰裁判長の「行きましょう」の一声で決まったものです。
現地調査は09年11月16日、原告代理人側から3人、国側代理人も3人、橋詰裁判長はじめ裁判官も同行しておこなわれました。セクハラ事件の審理のために、裁判所が自衛隊の基地内に入ったのは、歴史的にもこれが初めてのことだと思います。
●佐藤 事件が起きたボイラー室は、写真で見るより狭く見えました。われわれが入ったときは午後2時すぎで、外は明るいのに、照明を消すと機械室の中も事務室の中も光はほとんど入らず、人の存在や動きがわかる程度。原告が加害者から電話で呼び出されたあと、深夜に昇らされたという煙突に裁判長も昇り、15mという高さを実感しました。視察が許されたのはごく限られた個所だけでしたが、裁判長もわれわれも、原告の当時の状況や心境を推しはかってみる貴重な機会でした。
つらい証人尋問を乗り越えて
-すべての口頭弁論と進行協議が終わり、2010年はいよいよ判決の年となりましたが、その前におこなわれる証人尋問は、原告にとってやはり最大の難関だったのでしょうね-
●秀嶋 証人尋問は、加害者が2月4日、上司である1尉と3尉の2名に対する尋問が2月18日の午前と午後に、原告本人の尋問は3月4日の午前午後を通じておこなわれました。証人はそれぞれ、まず主尋問(自分の代理人から)を、その後反対尋問(相手側の代理人から)を受けます。
-1尉は通信電子隊長、3尉は電子小隊長ですね-
●秀嶋 今回のように加害者の尋問から始まることは、必ずしも多くありません。開廷前の2分間報道のテレビカメラが入り、そのあと、初めて加害者Aの尋問が始まりました。
この日の加害者の証言は、主尋問では、原告が合意していたという国の主張を裏付ける内容でしたが、反対尋問では、「なんとなく触ってしまった」「魔が差した」などと答えており、事件の事実関係については、おおむね認める内容のものでした。
弁護団は、原告の「明らかな合意」がなければ、それは性行為の強要であり、強制わいせつにあたる(つまり、セクシュアルハラスメントにあたる行為である)と当初から繰り返し主張していました。このことは最終弁論でも述べましたが、その意味で、加害者のこの日の証言で、性行為の強要があったことが裏付けられました。
●佐藤 2月18日の上司2人の尋問は、事件後の原告に対する「配慮・支援がきちんとなされたかどうか」に関する重要な尋問です。
この日、上司のひとりは「原告への事後の配慮はしたが、できないこともあった」「退職強要したわけではないが、志願書の提出を促すべきだった」など、わずかな非は認めました。
しかし、原告に対する上司たちの事後対応は、その程度の言葉で納得できるものではありませんし、明らかに原告を排除しようとしたものです。それはやはり、さきほど言った「精強さ」が彼らの根底にあるからだと思うんですね。
というのは、たとえば婦人科につれていく問題についても、「自衛隊としては必ず上司がついていかなければならないことになっている」と言うわけです。ある意味、2人の上司は正直な証言をしているわけです。けれどもそれは、原告本人の保護よりも部隊の秩序維持を優先した対応であり、原告はこのようにして部隊の秩序を乱した厄介者として排除されていったのです。
●秀嶋 しかし、性暴力やセクシュアルハラスメントの裁判で、原告(被害者)が法廷という公の場で証言することは、それ自体が被害者に対する二次被害にもなり、ひじょうに辛く、過酷な時間となります。原告は、これまで警務隊や検察庁で、自分の受けた被害を、繰り返し述べなければなりませんでした。そのうえ、3月4日の尋問で、新聞記者などを含む多くの人前で、被害内容を詳しく述べなければならず、国から60分予定されていた反対尋問も含めて、精神的にも体力的にも、彼女がどれだけ耐えられるか、率直に心配でした。
●佐藤 当日は、「支援する会」の申し入れにより、小さな法廷にしてもらい、証言台と傍聴席のあいだに衝立(ついたて)が用意され、原告が傍聴席や被告側の席の一部から見えないようにしました。原告の視界に入らないよう、傍聴に来た自衛官たちの席を移動させたり、原告の体調を見守るためSENE(セーン/性暴力被害者支援看護職)の看護士さんに原告側の席で待機してもらったり、できるかぎりの準備をしてくれました。
●秀嶋 原告は提訴から3年3カ月、自衛官のときも、自衛隊をやめさせられて札幌で働くようになってからも、仕事と通信制大学の勉強を両立させていました。休みの日には裁判のための書面づくりや、顔の見えない支援者のみなさんにお礼のコメントを書くなど、ほんとうによく頑張りました。防衛省への申し入れに、なんども東京へ行きましたし、全国各地で開いた報告会や勉強会にもたびたび姿を見せるなど、大切な青春の年月を、この裁判のために費やしました。
本人尋問のこの日も、原告はいっとき声をつまらせた時がありましたが、最後まで、凛とした声と口調で事件の内容を証言しました。「支援する会」の人たちも、「120%の出来だった」などと、原告をねぎらっていました。原告のたたかう意志の表れと感じた傍聴者も多かったのではないでしょうか。
原告が全面勝訴 人間味ある判決内容

勝利判決を勝ち取りました(札幌地裁前で 2010年7月29日)
-弁護団の先生たちの最終弁論もたいへん感動するものでしたが、なんといっても全面勝訴を勝ちとった2010年7月29日は、原告を応援した私たちにとっても大きな喜びの日となりました。法廷には大きな拍手がわきおこりました。この判決文(※9 骨子)の内容については、どのように評価できるのでしょうか-
(※9)判決骨子
【札幌地方裁判所 平成19年(ワ)第1205号事件・判決骨子】
1 道内某自衛隊基地内で夜勤中の男性自衛官が、階級の上下関係や建物の特殊な状況を利用し、基地内に住み込んで勤務していた女性自衛官の原告に対し、勤務場所で、性交に至らない性的暴行を加えた事実を認定し、かつ、その暴行が国家賠償法1条1項所定の違法行為にあたると判断し、被告国には200万円の慰謝料支払義務があることを認めた。
2 上記暴行後、原告所属部隊の職場監督者が、原告の婦人科受診を困難にした事実、加害自衛官を原告から遠ざけなかった事実、原告が職場に迷惑をかけたとして退職を強要した事実を認定し、これらの行為が国家賠償法1条1項所定の違法行為にあたると判断し、被告国には300万円の慰謝料支払義務があることを認めた。
●佐藤 判決が言いわたされた瞬間、原告は感動して目に涙をためていましたね。ほんとうによかった。
国は最後まで「合意のうえ」と主張して、「強制わいせつ行為」については全面否定していましたが、裁判所が「そういう事実があった」と認定してくれたことは、たしかに全面勝訴と言えます。けれども、われわれ弁護団がこの判決内容で強調したいのは、単に認めたということだけでなく、裁判所の認め方、判断の仕方がひじょうにすばらしいものだったということです。
つまり、性犯罪の裁判の場合、「合意のうえの行為かどうか」「どれだけ被害者が抵抗したか」など、そういう状況を重視することに判断が偏りがちです。具体的に相手をひっかくとか、その場から逃げるとか、そういうことでもないかぎり、応じたのではないかと認定されるような傾向が厳然としてあるのです。
それを、そうではないと。これだけ上下関係が厳しくて、20歳の女性がボイラー室に行くことをことわれなかった、従わざるを得なかったということをきちんと認定してくれたことです。これはじつは、すごいことなんですよ。
●秀嶋 そうなんです。今回の判決は、被害者が被害に遭ったとき、どのような状態に置かれるか、をとても丁寧に判断しています。
国は、原告が述べていた内容が、自衛隊内などで当初聴取したことと裁判後に述べた内容とで食い違っているので、彼女の言っていることは信用できない、と主張していました。
セクハラ裁判で必ずといってよいほど議論になるのは、被害者と加害者のどちらの言っていることが信用できるか、という点です。被害に遭うのは通常「密室」で一対一の場ですから、言っている内容が食い違うと、加害者・被害者のいずれかが嘘をついている、ということになります。
判決は、「性的暴行の被害を思い出すことへの心理的抵抗が極めて強いこと」「共感をもって注意深く言い分に耳を傾けないと、客観的事実と異なる説明やもっとも恥ずかしい事実を伏せた説明をしてしまうことはままある」「本事件に関する自衛隊の原告に対する事情聴取は、もっぱら男性上司や男性警務隊員によって行われており、原告が性的暴行を冷静に思い出したり、記憶を言葉で説明することができなかった可能性が高い」など、被害者がおかれた状況を踏まえ、原告が述べた被害内容の「信用性」についてひじょうに丁寧に判断しました。
この点も、大変重要な点です。本来は当たり前のことなのですが、残念ながら、まだ社会的には「当たり前」のこととして浸透していません。
●佐藤 もう一つは、被害そのものに対しての慰謝料と、事後の保護・援助がなされなかったとの不法行為に対する慰謝料とを、別個に評価し、それぞれに対して、200万と300万の慰謝料を認める判断がなされたことです。管理・監督責任についての被害額のほうが大きいという、これもまた画期的な判決内容です。
この判決がでたあと、全国でこういう裁判をやっている人たちからずいぶん問い合わせがあって、彼らはむしろこのことに注目しています。
セクハラ裁判の場合、ほとんどは相手が全面否認してくるので、「セクハラがあったのか、なかったのか」という議論に話が集約していきがちです。そのあとの会社の対応はひどかったんだと最初は言っていても、裁判をしているうちにだんだん、事後対応の部分の慰謝料を損害賠償の金額に反映させるところまでいかない。なし崩し的に和解で解決したりすることが、ひじょうに多いわけです。
そういうなかで、あとの対応の悪さまできっちり認定して、しかもそっちのほうが金額が大きいというのは画期的だと、彼らは言うわけです。そういうところで苦労してきた弁護士さんたちは、溜飲が下がる思いの判決だったと言っていました。
●秀嶋 私も同感です。加害行為だけの慰謝料だと、個人の責任のほうが大きい印象になりますから、その人が懲戒免職などで会社からいなくなれば、職場内では、それで「解決した」ことになってしまいがちです。会社は監督責任があるため、自ら慰謝料を支払うことにはなりますが、会社自身が、それによって更なる責任を問われたり、一層の防止策を講じていくという方向には残念ながらなっていないのが現状です。
今回の判決のように、事後の対応の違法性が認められ、これに対する慰謝料額が300万円であると判断されたことによって、組織の責任が明確になるため、今後組織として対応せざるを得なくなります。
被害者が被った二次的、三次的被害を、裁判所がしっかり受け止め、本来それを防止する責任が組織にあることを、はっきり示したわけです。
日本では、残念ながら懲罰的な慰謝料という制度がないので、アメリカのように、セクシュアルハラスメントによる企業が負担する慰謝料が何億円ということにはなりませんが、本来、懲罰的な慰謝料制度があれば、企業も自衛隊も、セクシュアルハラスメントが発生してしまった場合の『コスト』を考えたら、より防止に力を注ぐという発想になると思います。
今回、自衛隊は、加害者への懲戒処分すら、かなり時間が経った後の裁判中に、ひじょうに軽い処分で終わらせてしまっていますが、「加害者を懲戒処分にしたら終わり」では済まない、ということが大きく示されたと思います。
行政にも民間企業にも大学にもあてはまる
-国に対する判決がこのように出たことで、とうぜん、役所や民間企業で起こる事件にも同じことが適用できるのではないでしょうか。のちのちの裁判にも、リーディングケースとして大きな影響を及ぼすことになるのでは-
●秀嶋 そうですね。今回の判決は、事後対応の責任について、大きく一歩踏み込んだ判断をしていると思います。
今後、防衛省として、各現場レベルでの再発防止策を具体的に整備していく方向に転換しないと、原告が受けた被害が生かされない、この裁判が生かされない、そのような判断が裁判所にはあったと思います。判決は、裁判の性格上、個別の被害救済について判断するところまでですが、その中に、今後につながる内容を盛り込もうとした、裁判官の意欲、思いが伝わってきます。
もちろん、慰謝料額の500万円は、原告が被った被害内容と職場を失ったという重大な結果に照らせば、決して大きなものではありません。それでも、判決が、事後の国の対応も含めて総額500万円の慰謝料を認めたことは、これまでの性暴力に対する慰謝料額を底上げしていく意味があると思います。
1989年(平成1)の国内最初のセクシュアル・ハラスメント裁判といわれた福岡の事件から20年が経過しましたが、訴えた女性が被害者として適切に扱われずに職場を追われるケースは、現在まで変わっていません。
今回の判決は、そうならないために、公務職場であれ、民間企業であれ、大学であれ、実質的に機能するような体制をとるべきだ、という強いメッセージが込められており、その点でも、歴史に残る判決ではないでしょうか。
●佐藤 しかも、被害者を保護・援助する責任を、具体的に3つの義務に分けている。
1つは「被害排除義務」、つまり被害職員が心身の被害を回復できるよう配慮する義務。今回でいえば、きちんと産婦人科の病院に行かせる。2つ目は「環境調整義務」といって、加害行為によって当該職員の勤務環境が不快なものとなっている状況を改善する義務です。たとえば、加害者と隔離するとかですね。3つ目は「不利益防止義務」、これは性的被害を訴える者が、しばしば職場の厄介者としてうとんじられ、さまざまな不利益を受けることがあるので、その不利益を防止する義務ということです。原告に対する退職強要などはここに関わると思いますし、裁判の事実認定のなかには出てこないんだけれども、公的な行事に参加させないとか、そういうことはダメだと言っているんです。これは、今後の裁判にものすごく使えます。
●秀嶋 使えますね。
これまでの裁判では、雇用契約に付随する職場環境の整備義務(「安全配慮義務」)に違反したという抽象的な表現を用いることが多かったのです。
事後の職場環境の配慮をしなければならないということが、イジメや労災などの事件で出てくるのですが、では、何を配慮しなればならないかというところが、判決を見ただけで、一般の人には分かりにくいのです。被告になった企業などにも分かりづらい。
今回のように、3つの基準を打ちたてたことも、ひじょうに大きな特徴だと思います。どういうことをしたら義務違反になるのかが具体的にわかるように、という意識が働いていると思われます。ですから、セクハラだけでなく、パワハラとかイジメとか、いろんな場面で使えます。防衛省だけでなく、行政にも、民間にも使えるし、大学のキャンパス・ハラスメントにも使えます。
●佐藤 そうそう、これはパワハラで使えるんですよ。
●秀嶋 被害者がさらにダメージを受けるという二次被害、三次被害の構造の事件では、極めて有効な基準です。そういう意味でも、すばらしい判決でした。
勝訴と国の控訴断念を導いたもの
-国が控訴を断念した8月12日は、これによって7月29日の判決が確定し、この裁判がほんとうの意味で終わった日でした。原告はきっと、体のすみずみまで生命力を取りもどしたような解放感だったでしょうね。国(北澤俊美防衛大臣・民主党)が控訴を断念するに至った要因には、どのようなことが考えられるでしょうか-
●佐藤 勝訴の要因はいくつかあって、それがうまく合わさった結果として、国の控訴断念ということになったと思います。
僕が考えるいくつかの要素のひとつは、やはり2人の上司の証人尋問が大きかったと思います。さっきも言ったように、2人の上司は、ある意味で正直な証言をしているわけです。しかし、セクハラ被害者の保護という立場からいうと、20歳の女性が婦人科に行くときに男がついていくなんて、この感覚自体が時代おくれです。つまり、いまの世の中で、被害者の保護と、自衛隊の規律のどっちを優先するんだということが問われた裁判でもあります。
ですから、防衛省の人たちからみれば、証人尋問のなかでこんな証言をしてしまって、控訴したところでひっくり返せるだろうかと。かえって自衛隊にダメージになる裁判として残してしまう可能性がある、そういう判断があったと思います。
●秀嶋 それと、08年1月25日に東京の参院議員会館で開いた勉強会で、原告が超党派の女性国会議員の前で事件のことを訴えたことも大きかったと思います。このように、繰り返し国会や女性議員連盟に要請し、防衛省にも何度も働きかけを行った。そういう力が大きかったと思うんですね。また、一部の政治勢力、一部の議員団体が騒いでいるというのではなく、超党派で国会議員が動いたことが大きいと思います。
●佐藤 判決がでたあとの8月6日にも、原告は直接防衛省に行って国に控訴しないよう申し入れをしました。福島瑞穂議員と紙智子議員も同席してくれました。このとき対応したのは、中江公人防衛事務次官でした。09年8月末の衆議院選挙で民主党に政権交代したときに就任した事務次官です。事務次官が対応するということは、はっきりと控訴しないと結論を出していたからだと思うのですが、やはり原告が控訴断念を強く申し入れたことが大きかったと思います。
-自民党から民主党に変わったことも、影響したといえるかもしれませんね-
自衛隊が軍隊でなくてよかった
アメリカでは、アーレン・ワタダ陸軍中尉(当時28歳)が2006年6月に現役将校として初めてイラク派遣を拒否し、軍法会議に訴追される出来事がありました。ワタダ氏は9.11同時多発テロ後、愛国心から陸軍に入りましたが、イラク戦争が不正義と知ってイラク派遣を拒否したのでした。
軍法会議では一度は「審理無効」となりましたが、陸軍が再訴追したため、ワタダ氏は撤回を要求。連邦地裁は07年10月、ワタダ氏の言い分を認め、軍法会議の差し止めを命令しましたが、これに対し陸軍は米司法省を代理としてさらに不服を申し立てました。
しかしオバマ政権発足後の09年5月、同省が申し立てを撤回、陸軍も軍法会議の再開を断念してワタダ氏の除隊を認めました。ワタダ氏は同年10月2日に「不名誉除隊」となったものの、実質の「勝利」でした。
「米憲法」に照らしたワタダ氏の言動と、イラク戦争は間違いだったとする新大統領の登場がこの結果をもたらしたと当時のマスコミは受け止めたようです。
ワタダ氏は「自分の行動や信念について、人びとが十分に記憶してくれた」と表明しました。
●佐藤 今回の勝訴は、市民法廷の勝利だとも言えます(※10)。
たしかに、裁判所の法廷は単なる狭い一室ではありますが、基地の中に閉じこめられてひとりでたたかっていた彼女が、自分の人権問題を市民に理解してもらい、みなさんに応援してもらう場所になったわけですから。
ふつう、軍隊をもっている国では軍法会議があって、こういう部隊内の非行行為は軍法会議でしか裁かれません。軍法会議は、軍にそむいた者などは厳しく罰しますが、軍の恥になることは隠ぺいしがちです。一般の国民は傍聴ができませんし、弁護士だって資格制限されます。
日本は憲法九条があって、自衛隊は他の国で言う軍隊とは違いますから、自衛隊員も一般国民と同じ普通裁判所で裁判ができます。ですから、こうやって共感が広がり、支援が広がり、組織に妨害などをさせずに最後まで裁判ができるんですね。
原告も、勇気を出して市民法廷の場に出てきたからこそ、自分の人権を取り戻せたのです。「自衛隊が軍隊でなくてよかった」と言っていました。ほかの国ではこういう裁判はできないと思いますよ。
●秀嶋 裁判員裁判と軍事裁判所に関して書かれた論文を読みましたが、いわゆる軍事裁判所のような特殊な司法機関ができるようなことは、決してあってはならないです。自衛隊の「密室性」を高めて外から何が起きているかがわかりづらくし、自衛隊員の人権を抑圧する方向に働くでしょう。
-それはある意味、改善されるべき点があるということですか-
●佐藤 今回、自衛隊員がいざ懲戒処分を受けるというとき、かれらは自分を守る手だてがないということがわかりました。懲戒処分でも、やはり弁護士や代理人を認めるべきです。それから、警務隊の捜査ですが、警務隊はしょせん自衛隊の中の機能です。われわれの目が届かないところで捜査、処分が進みます。
僕はこれを一般の検察官やふつうの警察が捜査してもいいと思うんです。しかし、自衛隊はそれを排除する。自分たちでやると。
ですが、べつに法律を変えなくても、これは現行法の運用で可能になることです。とくに自衛隊の中の重要な事件、あるいは被害者が強く求めているときは、自衛隊のなかの警察ではなくて、外のふつうの警察に調べてもらいたいといえば、できると思います。こういうことは、おそらく現行法のなかでは問題がない。だから、そういう改善は可能だと思うなあ。
原告の裁判をきっかけに相談窓口が全国に

札幌で行われた「自衛官の人権裁判シンポジウム」 (撮影 三宅勝久)
-原告は提訴の決意のなかで、「自衛隊には労働組合もないし、被害者に不利な状況」と言っていました。原告は、国の一刻も早い改善を望んでいます。いま自衛隊内で原告と同じような被害に遭っている人たちが、安心して相談できる窓口はあるのでしょうか-
●佐藤 じつは3月4日、原告の尋問が終わったあと、札幌市教育文化会館で「自衛官の人権裁判シンポジウム」がおこなわれました。今回の彼女の裁判をきっかけに、海自「たちかぜ裁判」(06年4月提訴)、海自「さわぎり裁判」(08年8月提訴)、空自「浜松基地自衛官人権裁判」(08年4月提訴)の弁護団や裁判を支援する人たちが集まったのです。なかには家族や遺族の姿も見られました。
このとき、それぞれの裁判の経過や結果、苦労や課題などを公表し、励ましあって心をひとつにしたあと、「自衛官の人権裁判全国弁護団連絡会議」というのを結成しました。いちおう1年間は僕が事務局長を務めるのですが、これは女性自衛官のセクハラ問題にかぎらず、イジメやパワハラ、それによる自殺などの相談も受けます。すでに、小松基地の隊員が、パワハラを受けたとして自分で裁判を起こしたのですが、うまくいかなくて、いま名古屋の弁護士が代理人になってたたかうことになっています。
また、札幌では今回の「女性自衛官人権裁判」につづいて、「命の雫裁判」という新たな裁判が始まります。沖縄出身で当時20歳の男性自衛官が、初任地である札幌の陸上自衛隊真駒内基地内で、他の隊員から「訓練」という名の暴行を受けて死亡した事件です。
●秀嶋 自衛官が自衛隊(国)を相手にした裁判は全国で起きていますが、親族に自衛隊員がいるなどの理由で、表に出せずにいる当事者の方がかなりたくさんおられると思います。
原告は、同じ経験をした人たちのために役立てればとの思いももちながら、この裁判をたたかいました。佐藤弁護士が中心的に関わっている「自衛官の人権裁判全国弁護団連絡会議」もいま全国で10近い弁護団と連絡がとれて、受け皿が広がってきています。何かあれば、近くの弁護団に所属する弁護士に、声をかけていただければと思います。
-事件当時20歳だった原告は、今年24歳になりました。彼女の裁判は終わり、ふたたびたくさんの夢に向かって歩みはじめていることと思います。勝訴のあと、日本全国から喜びのメッセージがとどいていると聞きました。彼女を応援したたくさんの人たちも、きっと、原告のこれからが明るく幸せな人生になるよう、願っているにちがいありません。
原告が勇気をもって発した声は、いままた社会にいくつもの波紋を広げはじめています。自衛隊はそれを真摯に受け止め、自分たちのなかにある問題点を見直して、改善への努力を開始してほしいと思います。私たちも、それをしっかりと見続けていくことを忘れてはなりませんね-
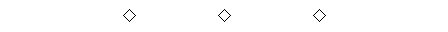
地裁判決の確定にあたって 2010年8月13日 原告
昨日8月12日に、国が控訴を見送るという判断をしました。これでやっと、私の裁判は終わりを迎えました。長く私を支えてくださった皆さんのおかげで、やっとこの日を迎えることができました。傍聴席まで足を運んでくれた方、メールや手紙で私を励ましてくれた方、まだ会ったことはないけれど、遠くからいつも私を応援してくれた方、そして私のすぐ傍で共に闘い、苦労を一緒に乗り越えてきた支援する会の皆さん、本当にありがとうございました。
すばらしい勝訴判決を頂いたのに、この2週間は何をしていても国から控訴されるのではないかという不安に悩まされました。佐藤弁護士に「控訴されたらすぐに連絡するから」と言われ、携帯が鳴るたびにもしかして控訴されたのではと怯えました。控訴しないでほしい! 早く裁判を終わりにしたい! と祈ることしかできませんでした。
そんな中、仕事そして共に働く仲間がいたことが、どれほど私の助けになったか解りません。仕事に集中していると裁判のことは考えられないのでそれが精神衛生上とても良かったと思います。
裁判を起こしてから2年後、自衛隊を事実上解雇となり仕事を探していた私に、裁判を通して知りあった方から仕事を紹介してもらい、現在もその職場で働かせていただいています。裁判を抱える私を、普通の人と同じように迎えてくれた今の職場には、感謝してもしきれません。
この裁判はさまざまな人が立場や思想を超えて、自衛官の私に共感してくれたからこそ、勝つことができたと思います。私を支援してくれた方は、私の話に耳を傾け、理解し、共感をもって接してくれました。本当に理解してほしいと思った自衛隊には最後まで私の言葉が届いたかどうか解りません。しかし、私が提訴したことで自衛隊の現状が少しでも改善されたらと願うばかりです。
私達が闘って勝ち取った判決は、戒めの楔(くさび)です。今後自衛隊は、自衛官一人一人を人間として扱い、決してその人権を侵害することがないように強く求めます。この判決が、自衛隊で働く人達への身体的精神的暴力・セクシャルハラスメント・いじめ等の抑止力になってほしいと思います。