ウェブマガジン カムイミンタラ
 2010年11月号/ウェブマガジン第30号 (通巻150号) [ずいそう]
2010年11月号/ウェブマガジン第30号 (通巻150号) [ずいそう]
「映画にかけた夢」~砂川 映画『エクレール・お菓子放浪記』を応援する5000人の会~
野嶽 次郎 (のだけ じろう ・ (株)プリズム映画事業部)
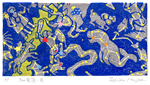
「冬の星座・昴」
版画:宝賀寿子
人は人生の中で何回ぐらい映画を観るのだろうか・・・。
映画が娯楽の王様と言われていた昭和30年(1955)代前半には、映画人口が年間12億人という調べがある。全国津々浦々、どんな小さな町にも映画館があり、活況を呈していた。映画産業の黄金期である。
映画には夢があり、銀幕に映し出される世界に人は憧れを抱き、時には励まされて生きてきた人も多いだろう。誰の心にも、忘れられない一本の映画があるだろう。
しかし、地方都市から映画館がひとつ、またひとつと姿を消した。
ここにひとつの夢をかけた取り組みがある。
かつて、上砂川、歌志内などの炭都を控え、人口三万五千人を超えた街、砂川市。この街にも最盛期には6館の映画館があり、賑わいを見せていた。この街からも映画館が姿を消し、人口も二万人を切った。かつての賑わいは道央自動車道の発達とともに、他都市同様、シャッターが下がり、空き店舗も目立つ。そんな街にも地元に根を下ろし、街おこしに情熱を燃やす人たちがいる。
昨年暮れ、縁があって映画上映が計画された。数年前から公共施設に35ミリの映写機が設置され、年に数回の上映会が催されてはいたが、ゲストを呼んでの上映会は初めてとあって、実行委員会の結成から上映までの約二ヵ月間、委員の人たちはチケット売りに奔走し、六百人を超える市民が映画を堪能した。
この時、ゲストとしてトークショーを行ったのが『ふみ子の海』の近藤明男監督と主演の鈴木理子さん。上映の合い間の懇親会で、砂川市長をはじめ、40名を超す市民が近藤監督が撮る次回作に『我が街で是非ロケを・・・』と熱望。その思いを監督にぶつけたのだ。
近藤監督の次回作が『エクレール・お菓子放浪記』(西村滋原作)だったことが、この街にとって幸運だった。約八年前、街おこしの一環として、国道12号線沿いの菓子店9店が「砂川スイートロード協議会」を立ち上げた。ある年の三月。“桜”をキーワードに、各店舗が独自の発想でお菓子を創作。パイやモンブランなど、アイデアあふれる商品が生まれた。また、地場産の食材を使った菓子作りや、地元の人たちへの感謝を還元として、30種類のお菓子を千円で提供する「スイーツフェスタ」を開催。賑わいをみせている。
こうした熱心な活動が監督の心を動かした。道南の観光地でのロケが決まりかけ、台本にも書かれていたが、この熱意が伝わり、砂川ロケの誘置が実現したのだ。
「映画は人に夢を与える」。まさにこの言葉は魔法であり、砂川市民に勇気を与えた。砂川市、商工業、一般市民を巻き込んだ一大イベントとして、「砂川・映画『エクレール・お菓子放浪記』を応援する5000人の会」(山本洋会長)が結成され、映画ひとコマ千円の募金活動、エキストラ出演、ボランティア協力など、ひとりでも多くの市民参加による砂川ロケの成功に向けて動き出した。
映画は完成まで目には見えない多くの人たちの協力と参加が必要である。わずか5分あまりのラストシーンの撮影のために、人口の4分の1、5000人の人たちが心をひとつにして一本の映画のために動く。参加した人たちは想像するのだ。「映画が出来、その後の砂川にとってどんな意味があるのだろうか・・・」。
この運動の中心的役割を果たしている砂川まちの駅連絡協議会の信太勝見事務局長は、「ただ、映画ロケのお世話をするというだけではなく、多くの人とその思いを共有し、これからの砂川の姿、あり方を考えるきっかけになる。映画を通して全国に砂川のまちの魅力を発信し、自分たちの街の魅力の再発見につながることこそ、この映画づくりに参加する大きな意味なのです。」と…。
なにしろ、すべてが初めての経験。眠れぬ日々を過ごし、右往左往し、暗中模索の中で、5000人の市民の思いをひとつにしてこの映画の成功にむけて歩き出した砂川。
この取り組みが、全道の小さな町に勇気を与え、「オラがマチに映画が残した財産」として、どのように変化するのか・・・。
きっと名作映画を観終わった後のように、さわやかな感動が人々の心に残る取り組みになるだろう。
