ウェブマガジン カムイミンタラ
 1998年11月号/第89号 [特集]
1998年11月号/第89号 [特集]
母のように優しく豊かな大地に山岳美の極致を追いぬくもりと詩情を伝える
大雪山を撮る
『頂上の偉大なること天下に比なく、群峰集って天を刺し、ただに北海道の十国島に冠たるのみならず、九州になく、四国になく、中国になく、近畿になく、奥羽になし。信濃を中心とする諸高山には劣るも、緯度高きをもって山上の草木風物は信濃付近の高山と匹敵する』と大町桂月によって大雪山の大きさが天下に知らされて以来、多くの人はこの山岳の深さ、美しさに魅せられてきました。四季さまざまに変容し、あくまでも崇高なこの山の真実と向き合う、函館市出身の山岳写真家・市根井孝悦さんは、9月上旬のある日、層雲峡ロープウェイ(〒078-1701上川町層雲峡 TEL:01658-5-3031)の始発に乗り込み、リフトを乗り継いで黒岳山頂に達しました。めざすのは雲の平、北海岳の裾を経由して白雲岳へ。こんどの撮影目的は、ピークの紅葉と冬ごもりの支度に余念のないシマリスの営みをとらえること。重い装備を背にして進む市根井さんの眼前には、澄みきった秋空が広がっていました。
“神々の遊ぶ庭”をとらえた2冊の写真集

市根井さんは1回の山行に4×5インチフィルム300枚、サブに35ミリフィルム多数を持参する
北海道の中央に位置してその屋根をなす大雪火山群、十勝岳を中心とした十勝火山群、然別湖を抱く然別火山群、さらに石狩岳山群など一帯は、1934年(昭和9)、日本最大の山岳国立公園に指定されました。その名は「大雪山国立公園」。面積は2308.9平方キロメートル。東京23区とその周辺都市に、神奈川県の川崎市、横浜市、横須賀市までも加えた面積に相当します。

1988年に刊行された写真集『大雪山』
(山と溪谷社発行)
その中心をなす大雪山群は、最高峰の旭岳(2290メートル)をはじめとする標高2000メートル級の山々20数座によって形成されています。原住民族アイヌの人たちは、この山群を「うねり流れる川(日本第2の長流・石狩川)の上にそびえ立つ山」を意味する『ヌタクカムウシュペ』と名づけ、その山上に点在する湿原や沼沢、華麗な高山植物が群生するお花畑と雪渓が広がる山頂部の大地を指して『カムイミンタラ(神々の遊ぶ庭)』とも呼んでいました。その魅力をいかんなくとらえて1985年に処女作『大雪・石狩・十勝』(山と溪谷社)、88年に『大雪山』(同)を出版したのは函館在住の市根井孝悦さん(59)です。この写真集は版を重ね、前書は3万5千部、後書も完売となりました。
高山植物が咲き乱れる山頂の様子を生徒に見せたい
市根井さんが大雪山に魅了されたのは、高校3年の夏からだと言います。

黒岳や白雲岳周辺コースは市根井さんの好きな撮影ポイント
「大雪山天人峡からトムラウシ山を往復し、五色ヶ原、忠別岳、白雲岳、黒岳を経て層雲峡に下山する縦走登山の途中で横なぐりの雨と強風に遭い、ようやくの思いで白雲岳にたどりついたのです。白雲石室(現白雲避難小屋)に泊まった夜、ふと目覚めて外に出てみると満天の星。夜明けとともに、眼下に見えるトムラウシ山。そして、十勝岳連望が赤一色に染まっていく。その美しさ、崇高さが私を大雪山のとりこにしたのです」。
高校を卒業した後、市根井さんは北海道教育大学函館校に入学しました。ところが、在学中の1962年冬、大雪山遭難史に特筆されるほどの遭難事故が起きたのです。大晦日から元日にかけて旭岳陰の斜面を登っていた教育大函館校の学生パーティー11人が、想像を絶する大暴風雪に襲われて10人もが遭難死。助かった1人も凍傷にやられて両足首を切断するという痛ましい事故でした。市根井さんの山岳部の仲間たちでした。「その中には、当時、最も敬愛していた菊地夷彦君がいました。彼の遺体はなかなか発見されず、最後に雪渓の中から掘り起こされました」というつらい思い出があり、それ以来、市根井さんにとって大雪山は特別な存在にもなっているのです。
1963年に大学を卒業後、1878年(明治11)にフランス聖パウロ修道女会の修道女3人によって開設された伝統ある私立女子高の函館白百合学園高等学校に生物科の教師として就職。早速、同校山岳部の顧問にもなりました。この顧問は長く務め、北海道高体連登山部の生みの親で旭川市在住の速水潔さん(80)との親交を深めながら研鑽を積み、1979年と81年の高校総体女子山岳競技で優勝監督になっています。
大雪山の撮影をはじめたのは、教師になった翌年の1964年からです。

黒岳9合目から凌雲岳、上川岳を望む
撮影/市根井孝悦さん
「2000メートル級の山に行くと、その山肌を包んで、一面、色とりどりの高山植物が群生していますが、生徒たちはその様子を想像することさえできないだろうなと思ったのです。ぜひ生徒たちに見せたいと思い、スライドに撮ってきて、高度が増すにつれて植生が変化していく様子などを生物科の教材として見せたのです。手にしたのは購入したばかりの35ミリ判カメラ1台。まだ写真についての特別な知識も技術もないころでしたが、そんな中に自分でも驚くほど良く撮れたと思い、私を山岳写真の世界にのめり込ませる写真がありました。無謀にも、いつか写真集を作ることができるのではないかと思い、山に通いはじめたのです」。
「そのころの写真で、いまも残っている1枚はエゾツガザクラを撮った写真。もう1枚は、黒岳の頂上から凌雲岳を見ているとき、太陽が出てきて気温が上がり、下にあった雲がぶぁっーとわき上がってきたときの写真で、それはものすごい光景でした。いまにしてみればそれほどでもない作品ですが、そのころの私は、この2点によって山岳写真をずっとつづけていけそうな気になったのです」と振り返ります。そして、決定的な確信を得た作品は、そこに選ばれるのがプロ写真家としての登竜門ともなっている、山と溪谷社の『アルペンカレンダー』77年刊に特選となって掲載された「紅葉のヤンベタップ」です。
ヒグマと至近距離で遭遇し、仁王立ちになってにらみ合う
本格的に大雪山詣でをはじめたのは、1965年からでした。
市根井さんが山に入ると最低でも10日ほど、ふつうは2週間くらい滞在します。そのため、それだけの期間を山で耐えられるだけの食料、燃料、撮影機材を装備して行くのです。
カメラは、ドイツ製カメラのリンホフマスターテヒニカ4×5だけ。視点が変わるのでリンホフ1本に絞っていましたが、最近は35ミリカメラの性能が向上して表現力を増したので、最近はサブとして併用しています。レンズは10本くらい。さらに三脚を持つので、機材だけで重量は18キロほど、装備全体では40キロにもなります。長期間の山ごもりになりそうなときは、食料などを二度にわけて運び、避難小屋などにデポ(留置)っておくこともあります。
山行で最も大変なのは、なんといってもヒグマとの遭遇と厳冬期の撮影です。
「山岳写真の撮影条件は、日の出後と日没前が重要なポイントです。そのため、星明かりの中での行動が多く、時には夜間に登って日の出前に撮影地点に着いていなければならないこともあります。勢い、夜行性のヒグマと遭遇する確率は高くなります」。
最初のころは、クマと300メートルくらい離れていても、怖くて撮影をすることができなかったと言います。ところが、ある夏、ヒグマの成獣と面と向かって出遭ってしまいました。大雪山系五色岳を過ぎて化雲岳に向かうハイマツの廊下の中でばったり。両者の距離は7~8メートルくらいだったとのこと。「その距離が幸いしたのです。もし5メートル以内に接近していたら、やられたにちがいない」と市根井さんは言います。

1回の山ごもりはふつう10日くらい、冬は機材や食料など装備は約40キログラム になることも
「ヒグマの方も私に出遭って驚き、おたがいにグワァーッと仁王立ちになったのです。立ち上がってはみたものの、7メートルという距離のために余裕があったのでしょうか。ヒグマの眼は血走って真っ赤ですし、口からはよだれを垂らしている。ヤバイと思って逃げたら、きっとやられていたと思うのです。しかし、こっちは恐ろしさに立ちすくんで動くことなどできず、何も言うこともできず、ただにらみつけていたんです。すると、ヒグマの方はキョロキョロしはじめた。ああ、むこうも怖いんだなと思ったのでちょっと視線をずらしてやると、さっとハイマツ帯に逃げて行ったのです」。このことがあってからは、クマがあまり怖くなくなったとのことです。
吹き荒れる白魔の世界で1週間もビバークする

白雲岳からニセイカウシュッペ山、黒岳を望む 撮影/市根井孝悦さん
「冬、大雪山に入るのはかなり大変なことです。たとえば、層雲峡からロープウェイに乗って白雲岳に行くとしたら、夏なら日帰りコースです。ロープウェイからリフトを乗り継いで七合目まで行くと、黒岳までは夏なら1時間で行けるのに、冬は朝から1日がかりで黒岳石室まで行くということになります。途中で吹雪かれ、九合目で雪洞を掘ってビバークしたこともあります」。
「黒岳山頂から石室へ行く途中は季節風が強く、まともに北風をうけていると意識が朦朧(もうろう)としてきますし、からだごと吹き飛ばされてしまうこともある白魔の世界です。黒岳の石室はすっぽり雪に埋もれていて、窓のところに長い棒が立っています。それを目印にして雪を掘り出して出入り口をつくります。部屋の中もすき間から雪が吹き込んでいるので箒(ほうき)で掃き出して寝場所を確保し、次の晴れ間を待って白雲岳まで行くのです。途中の美ヶ原、北海平も、吹雪かれるとコースがわからなくなります。
1996年1月8日、白雲岳を発ち、北海岳の壁を下山中に記録的な大暴風雪に遭い、前進不能になってフォースト・ビバークしました。しかし、テントは破られ、雪洞の中で2日半の食料を食いつないで、1週間も耐えたことがありました。
「ふつう、日が暮れる3時間前くらいまでにベース地に到着して休息するのが安全登山ですね。しかし、写真家の場合は最も危険な夕暮れごろは撮影場所にいるのです。ですから、自分のイメージどおりの写真を撮ろうとすれば命がけです。いつ山の神に生命を召されても不思議ではない、そんな世界に身を置いていることをいつも感じさせられています」。
それでも、市根井さんは35年間、山に入りつづけているのです。
豊饒の夏、絢爛の秋、猛吹雪のあとの晴れ間の爆発
市根井さんを魅了してやまない大雪Rとは、どんな山なのでしょうか。
「大雪山の全体像は、日本アルプスに象徴されるようなゴツゴツときびしい山ではなく、山というよりは丘陵地帯という感じです。それだけに、豊かで優しさをたたえた、母のふところに抱かれているような気分を人びとに与えてくれる山」だと言います。
大雪山の早春は、6月初旬から中旬。雪解け水によって流れができ、植物たちがどんどん芽を吹いてきます。外気はまだ寒いのだけれども、いちばん早く咲くのは、黄金色の花のエゾノリュウキンカや白緑色の花を穂のようにつけるミヤマバイケイソウなど。まるで母の胎内から生命が誕生し、育んでいくような自然の営みに感動せずにいられません。
少し早いのですが、6月中旬から8月下旬までを、市根井さんは大雪山の夏としています。7月になっても急斜面には巨大な雪田が残り、そのまわりは一面に高山植物が咲きそろっています。お花畑の最も美しいのは7月中旬過ぎから。市根井さんが特に好きだというこの季節には、白雲避難小屋の周辺にキバナシャクナゲ、白い花のチングルマ、紅紫のエゾコザクラ、紫のエゾオヤマノエンドウ…、数えあげたらきりがないほどの高山植物が、文字どおり百花繚乱と山肌を飾って、光と花の饗宴となります。本州の山では味わうことのできないそのスケールは、まさに神々の遊ぶ庭と呼ぶにふさわしい豊饒の季節です。
錦秋―。ハイマツの濃い緑、ダケカンバの金色、ナナカマド、ウルシの赤…、大雪山の秋は絢爛です。8月下旬になると薄氷が張って、紅葉がはじまります。最も早い紅葉は、山頂付近のウラシマツツジ。まだまだ日中は気温が高いのですが、夜になると霜がおりてキュッと気温が下がるので、それはみごとな鮮紅色に輝くのです。本州の山の紅葉は、くすみます。しかも、大雪山の紅葉の規模は広大です。特にすごいのは大雪高原温泉と、すぐそばのヤンベタップ沢の源頭。一帯は火山灰地なので、大雨が流れて深く削られてできた“雨裂”が赤と黄に輝き、錦帯のようになって斜面を走るのです。それとは対照的に「初冠雪などに被われた山地にわずかな残り葉だけをつけたダケカンバの白い幹など、老境の寂寥感を感じさせる風情も好きだ」と市根井さんは言います。
そして冬の大雪山はまさに神々の座であり、「そこに神がいるのが感じられる」というのです。
大雪山の気温は思ったほど低くはありません。1月から2月にかけての平均気温は氷点下20℃くらい。酷寒の時でも氷点下30℃まで下がることは珍しいようです。下界の旭川市郊外のほうが氷点下40℃近く“しばれ”ることもあります。しかし、山では、風がつくと別です。風速25~30メートルの強風が吹くと、体感温度は氷点下50℃以下というのが常識の世界です。鼻にはつららが下がり、耳や顔などは外気に触れると即座に凍傷に罹ってしまいます。そんな暴風雪は1日や2日でやむことなどめったにありません。そのきびしさは、とうてい言葉では表せないのです。
「寝袋の中で、イモムシのようになって寒さに耐え、1週間以上もつづく猛吹雪の晴れる瞬間を待っている。ある日、急に青空が広がる。それを見たときは、まさに“爆発”という表現がぴったりの感動に奮い立つのです」とも。
酷寒の中での孤独が山岳写真への姿勢を変えた
「写真芸術は、たかだか150年の歴史と新しく、絵画など他の芸術領域に比べてじゅうぶんに評価されていない面があります。しかし、美と真実を追求した1枚の写真が人びとの心に与える感動の大きさ、深さはどのジャンルの芸術作品とも比肩できる力を持っていると思うのです。それだけに内面をどんどん深め、あるいは高めて、多くの人に感動を与えることのできる作品を撮りつづけたいのです。大雪山は現在の私にとっては最高の被写体であり、そこに内在する山岳美の極致を追い求めていこうと思っています」と、その思いを語ります。

思い出の写真集ノ目を通す
「フィルムを媒介にして大雪山をどのように表現するか。写真を撮りはじめて日が浅いころは、ことさら人間臭を排除して、きびしい山の姿を表現しようとしていました。しかし、酷寒の中で長いあいだ一人暮らしを強いられていると、ひと恋しさがつのり、たとえ他人の排泄物であっても、それを見ると、ここに人がいたのだという懐かしさが込みあげてきます。そんな体験を積み重ねていくうちに、私の山岳写真に対する姿勢は少しずつ変化していきました」。
「私の山の写真は優しいと言われます。たしかに、だれもが容易には行けないようなポイントから撮って冒険心を煽るような作品も山岳写真ですが、切り立った岩壁などの険しさも地球12,500キロメートルの直径に比べたら、どれほどのことなのだろう考えたりしてしまいます。あるいは、地球を1つの生命体と見た場合、その上に存在するすべてのものによって共同体が構成されていることを思わなければならないと考えてみるのです。すると、黒岳山頂付近や石室下のキャンプサイトで人を怖がらずに愛らしく走り回っているシマリスやそのほかの動物たち、可憐な姿からは想像できないほど強じんな地下茎をガレ地深くに張っている高山植物たちの生命力、凍てついた枝先にしなびかかった赤い実をつけて頑張っているナナカマドの姿に、いとおしさが湧いてきます。そんな自然の息づかいや営みにレンズを向け、人間のぬくもりと詩情が伝わってくる作品を撮りつづけたいと、私は思っているのです」。
夢は「世界の大雪山」を各国へ紹介すること
市根井さんは、昨年3月、教職を辞して、岳人・山岳写真家ひと筋の道を歩きはじめています。しかし、生徒たちと過ごした34年間の充実した教員生活、なかでも90年に写真部を創設し、顧問教師になって以来の生徒たちとの交流の思い出は、いまも心の中に大きな存在感となって残っているようです。
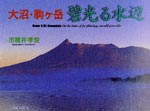
刊行まもない写真集(発行・北海道新聞社)
「私の写真人生を振り返る時、教師として奉職中にいかに多くのことを教わったか、に思い至る。とりわけ顧問をした函館白百合学園高・写真部の生徒、なかでも第2回写真甲子園を全国優勝に導いた飯塚麻紀、第3回大会で準優勝を果たした澤見輝恵などの生徒から逆に多くのことを学んだ。彼女らの固定観念に囚われない柔軟な発想は驚きであり、この出会いが私の写真を変えた。それだけに共に被写体を求め北の大地を駆け巡った日々は、私の人生の最も大切な一こまになった」とあとがきに述べた退職後初の写真集『大沼・駒ヶ岳 碧(みどり)光る水辺』の作品は、その心境や内面が反映されているように見えます。また著者プロフィールに掲載した市根井さんのポートレートは、教え子の撮った写真です。
プロ写真家となった市根井さんは、いま、山と溪谷社から2000年に出版を予定している『日高山脈』『大雪山』『北国の名峰たち(仮称)』三部作のまとめに取り組んでいます。そしてもう1つの夢は、大雪山を“世界の大雪山”として海外にも広く知ってもらうこと。最初は、カナダかアメリカで個展を開いて紹介したいとのこと。そのためもあって『碧(みどり)光る水辺』のキャプションは、2カ国語を採用しています。それが実現されたらアラスカを撮って日本に紹介したい、という夢に向かって進むとのことです。
心を写すことの大切さを教わりました
函館白百合学園高等学校写真部
元部長 飯塚 麻紀さん(仙台市青葉区在住)
市根井先生に、教師として身近に教えを受けるようになったのは、高校2年の『生物』の授業からでした。生徒にとってはとても面白い先生でした。写真部の顧問をされているのは知っていましたから、写真部に入ったら楽しいだろうなと思い、誘われるままに入部したんです。最初の年は、畑仕事をしている農家の人や子どもなど「ひと」を撮っていました。先生は「写真は心を写すものだ」と、とてもきびしくおっしゃり、ご自分も人を撮っていました。きっと先生は人を撮るのがすきなんだなと思っていましたら、山岳写真家としてすばらしいお仕事をたくさんしていることを、あとで知りました。
高校3年の時、こんどは函館近郊の大沼国定公園で、花や風景写真を多く撮るようになりました。私はいちばん不器用だったので、構図の決め方からアップの撮り方、表情や全体をどのように撮るかなどずいぶん厳しく教えられたのですが、いまも残っているのは楽しかった思い出ばかりです。
写真部での活動は2年間でしたが、私にとって忘れることのできないのは、旭川市の近郊、東川町で開かれた『写真甲子園‘95』での優勝です。それは先生にとっても同じだったかのしれません。
撮影最終日のテーマは「人間」でした。私は被写体になってくれる人を求めて病院を訪ねましたら、病室のベットに横たわっていたおばあさんが、私に「来てくれて、ありがとう」とお礼をいうのです。人に会うことをこんなにもうれしそうにするその表情に、晩年を病院で過ごす人のさびしい気持ちがひしひしと胸に迫り、涙が止まりませんでした。やっとの思いでシャッターを切った時の写真と、部員が心を合わせて撮った写真が評価されて“金のモモンガ賞”を受賞したんです。「写真は心を表現するのだ」という先生の教えが、このとき一気に花開いたのだと思います。
いま、先生は教職を退職されて写真一筋の道を歩まれています。私は今年からお勤めをしてカメラから離れた仕事を勉強中ですが、先生のすばらしい作品から、人としての大切なことをもっともっと教わっていこうと思っています。
